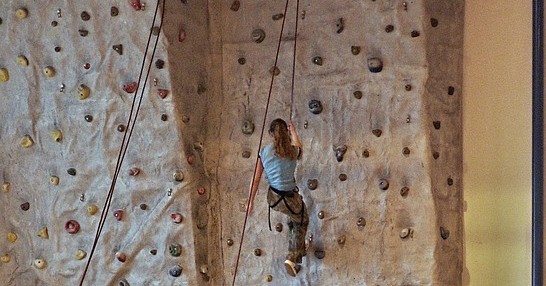7月からはじめる代替の勉強メニューを2つ紹介します
7月8月、口述対策にイマイチ身が入らない受験生のための代替の学習メニューです
未設定
2025.07.11
読者限定
いつもお読みくださいましてありがとうございます
背中がバキバキです(泣)