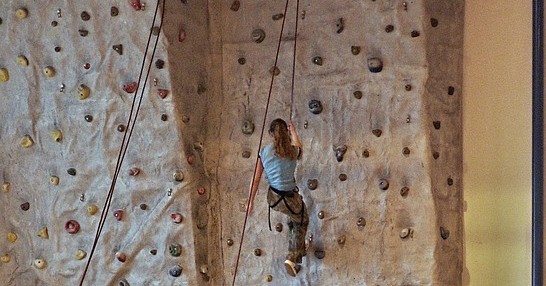7・8月に条文説明問題の過去問演習をする理由を説明します
現実的な口述対策も、あわせて解説します
未設定
2025.07.11
読者限定
いつもお読みくださいましてありがとうございます
毎日毎日、「もうこんな時間」です
この記事は無料で続きを読めます
続きは、5494文字あります。
- 1. すべての受験生が7月に「条文説明問題」を演習する理由
- 2. 口述合格は「直前3週間の対策」のみで間に合うのか?
- 3. 「およそ4人に3人」は論文式試験対策を続けるという現実
- 5. 夏からの「はじめての論文式試験対策」としても、条文説明問題の過去問がベスト
すでに登録された方はこちら