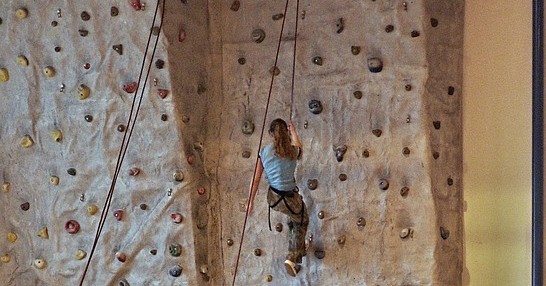合格答案を「シンプルに」考える (1)
合格ラインを超える答案を仕上げる上での改善点を、3つご紹介します
未設定
2025.07.17
読者限定
いつもお読みくださいましてありがとうございます
今日から2~3回に分けて、本試験で合格ラインを超える答案を4通書くための3つの改善点を考えていきます