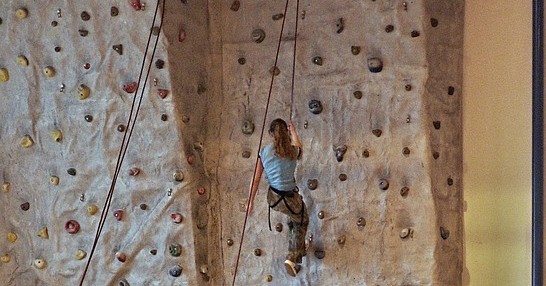論文式試験の答案を書く時の「1パターン」
どの科目・どの出題テーマでも使える解き方の基本をマスタしましょう
未設定
2025.07.12
読者限定
この記事は無料で続きを読めます
続きは、2505文字あります。
- 1. 「問題を把握する」ためには、形式面をチェックした後に、設問表現にアンダラインをする
- 2. 「趣旨」が問われたときの1パターンな答案構成
- 口述試験なら、「問題点⇒そこで」を解答すればOK
すでに登録された方はこちら