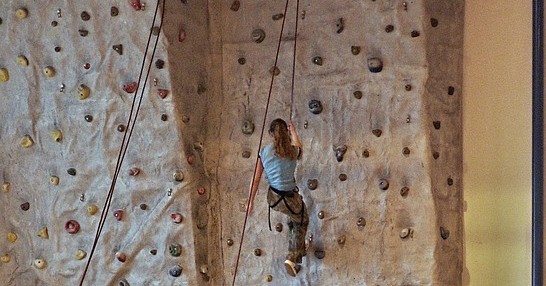令和7年の論文式試験を解きながら考えたこと (2)
いつもありがとうございます
引き続き令和7年の弁理士試験の論文式試験を解いていきます
今日は特許・実用新案の2通目です
問題文のボリュームは1通目よりも多く1.25倍くらいはあります
今年に限らず、「1通目をスピーディに解答する」のは特許・実用新案で高得点を取るために必要な考え方です
1通目を解く時、解答を書く時には、
「2通目に時間を回す」
と念じるようにしたほうがよいです
(前回の1通目の解説も、この観点でもう1度読み直してみてください)
それでは、2通目の問題の中味を見ていきましょう
問II1は25点分なので、解答量は1ページが目安です
事案は複雑ではないですね
甲:特P
乙:専P
丙:123② (∵123①2 29②違反)
で、問1(1)は「甲のPに係る特許 vs 丙の無効審判請求(123①柱)」に対し、「乙が関与できるか」が問われてます
この関与は「参加」(149①)で、「甲の味方 or 丙の味方」の2パタンがあります
答案構成は、
問1(1)
1. 結論:できる
2. 当事者参加
3. 補助参加
でいいでしょう
問1(2)へ入ります
問1(2)については事案の把握に戸惑いました
乙が「甲の主張とは異なる主張をする」こと自体は、特許を無効にする当事者参加人としての立場であっても、特許を維持させる補助参加人の立場であっても可能です
ただし、問題文には、「甲の反論の主張」が「適切かつ十分」か「実効性に疑問」をもって乙が主張をする・・・ということは、甲の味方としての主張=補助参加ですね
補助参加人が「一切の審判手続」ができると規定してる148④を解答すればよさそうです
答案構成は、
問1(2)
1. 結論:できる
2. 148④
で、理由付けは、乙は「一切の審判手続」ができるから、「甲と異なる主張」もできる、程度の「浅さ」で終えます
問2に入りましょう
設問表現をチェックし、「以下の設問に答えよ」と、各設問が「それぞれ独立」にマークします
こうした当たり前の設問表現も「普段通り当たり前にチェック」するのが平常心のキープに役立ちます
問2(1)は、「当該請求は認められないだろう」という立場で、「当該請求が認められない理由」を「具体的に説明せよ」にアンダラインを引きます
その上で「請求」が何かを確認すると、「特許権Pの持分の移転請求」だと分かります
ということは、
74①NGの理由⇒特許を受ける権利(29①柱書)がない
という解答の流れになりそうです
また、問われてるのは「持分の移転請求」だから、共同出願違反(38条・123①2)のみを解答すればよさそうです
解答量については、問2は小問が3つで75点の配点なので、問2(1)だけで最大25点分の配点があると見込んで「やや(比較的)タップリめ」に解答することもあるかなと考えました
続いて問(2)、「次の問いに答えよ」はアンダラインで、「抗弁事由については検討しなくてよい」が波線です
抗弁事由を答えないということは、侵害の成否だけを解答すればよさそうです
問2(2)(a)は「特許権Pに基づく差止請求は、どのような場合に認められるか」で、問2(2)(b)は「特許権Pに基づく差止請求ができるか」ですから、冒頭で100①に言及した上で、小問ごとに解答すればよさそうです
その小問を見ていくと、問2(2)(a)は「乙vs丙」で、問2(2)(b)が「乙vs甲」だと分かります
ここまで設問を把握した上で、問2の事案整理をします
Pのロは単純方法の発明(2③2)で、問2(1)は移転請求をした「甲がロを発明してない」という視点で事実を探して解答します
ロの発明特定事項を見ていくと、「ロ=γ=β+C」で、βは甲の発明だけどCをしたのは乙のみだから「乙のみがロを完成させた」=「ロに係る29①柱を持つのは乙のみ」と問2(1)は解答できます
問2(2)の事案では、丙は「業者」なので「業として」(68条)の要件は満たしそうです
その丙は「βを使用」してますが、「ロを使用」してるというためにはCをやっている必要があります
単純方法の発明に係る特許権の行使だから「カリクレイン事件」は念頭にあるものの、問2(2)(a)では「(差止)請求の対象となる行為」を特定して解答すればよいので、「Zの販売」が差止請求の対象ではないことをわざわざ解答する必要はないです
ということで、問2(2)(a)は、
問2(2)
100①
問2(2)(a)
1. 「業として」(68条)
2. 「βの使用」+Cをすれば差止OK
の順に解答します
一方で、問2(2)(b)は「乙 vs 甲」で、その甲は「βの貸渡し」しかしてないから、特許発明ロの使用をしておらず、間接侵害(101-4/5)が解答の中心になります
間接侵害が問われたときは、「直接侵害してない⇒間接侵害の検討」の順に解答します
また、問2(2)(b)では「(a)の差止請求が認められる」ことを前提に解答するので、甲の行為の相手方である丙の直接侵害が成立しています
この事実は従属説の解答として使えます
答案構成としては、
問2(2)(b)
1. 直侵(68条)しない
2. 101-4「にのみ」非該当
3. 101-5 該当
4. 従属説
5. 結論
の流れで解答していきます
このうち101-5は解答するための要件が多いため、解答スペース・解答時間は十分に確保したいです
ということは、101-5に入るまでの解答は総じてアッサリ書きたいです
とにかく、
「後半の問題に向けて解答時間・解答スペースを余らせることができれば勝ち」
このことは科目を問わず忘れたくないです
最後に、特実2通目の答案構成をまとめておきます